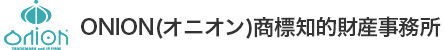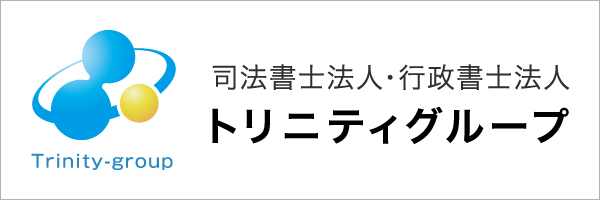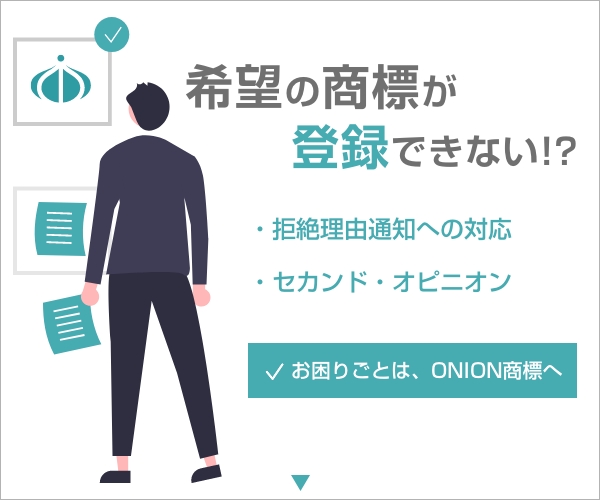ONION商標・弁理士の山中です。
技術革新等に伴い変化しつづけるエンタメ業界。そんな時代だからこそ、拠り所とすべきは「著作権法」ですが、「法」に対していきなり細かいところをつつくのではなく、「その全体や構造、考え方を『ざっくり』学んでしまうことが近道だ」という趣旨でご紹介する連載、その第15回です。
数回にわたって、著作権の「制限規定」についてご紹介してきましたが、
第7回「他人の著作物を使っていいケースとは?ー著作権の制限規定(その1 :概要と「私的使用のための複製」)
https://onion-tmip.net/update/?p=1192
第14回(前回)「他人の著作物を使っていいケースとは?ー著作権の制限規定(その8:美術関連の制限規定)」
https://onion-tmip.net/update/?p=2909
…だいぶ大詰めですね。今回からは、
【デジタル時代の?制限規定】
を見ていきたいと思います。
デジタル化・ネットワーク化の進展等に伴う著作物の利用環境の変化を受けて、著作物の利用の円滑化を図る観点から、「こういうケースは、(条件ではあるものの)自由に誰でも著作権が利用できるようになったほうがいいよね」ということで、平成末期から法改正(制度改正)が順次行われてきました。
たとえば、平成24年(2012)の改正で加わった制限規定(※後にさらに改正あり)としては、以下の2つなどがあります。
第30条の2 付随対象著作物としての利用
まず1つ目のこちら、条文が複雑なので省きますが、要は、
写真撮影、録音・録画、放送等を行う際、本来意図した対象以外の著作物が「写り込む」場合は、セーフ
というものです。対象として撮影等した著作物(※利用許諾を得ているもの)の背景に、他の著作物、たとえば絵画が小さく写り込んでしまうとか、音楽が入り込んでしまうとかといった場合に、その写り込み等したものを自由に利用できる=権利侵害としない、という制限規定ですね。もちろん、要件はあって、以下にあてはまらないといけません。
1 写真撮影、録音・録画、放送等の方法によって著作物を利用するにあたっての複製又は複製を伴わない伝達行為であること
2 メインの著作物に占める割合や再製の精度等に照らし、軽微な構成部分であること
3 付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無や分離の困難性等の程度、付随対象著作物が果たす役割等に照らし、正当な範囲内の利用であること
4 その付随対象著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと
続いて2つ目はこちらです。
第30条の3 検討の過程における利用
著作権者の許諾を得て、又は裁定を受けて著作物を利用しようとする場合に、
著作物の利用について「検討を行うために」著作物を利用する場合は、セーフ
という制限規定です。たとえば、ある著作物(マンガのキャラなど)の商品化を検討するときに、会議用の資料とかにそのキャラを掲載したりすることがありますよね。検討段階だから当然、まだ著作権者から許諾は得てない段階ですので、厳密に言えば複製権や譲渡権の対象になってくるところを、自由に利用できる=権利侵害としない、という制限規定ですね。もちろん、要件はあって、以下にあてはまらないといけません。
1 著作権者の許諾を得て、又は裁定を受けて著作物を利用しようとする者であること
2 許諾を得て、又は裁定を受けて行う著作物の利用についての検討の過程における利用に供することを目的とすること(「検討の過程」には、著作権者に許諾を申し出る際に作成される資料における著作物の利用も含む)
3 必要な限度内のものであること
4 その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害しないこと
なお、結果的に、企画が実現しなくても、セーフです。
これらは、デジタル化・ネットワーク化の進展などを背景に、著作物の利用行為が飛躍的に多様化する中で、「形式的には違法」となる著作物の利用を権利制限する=セーフにすることで、利用の委縮を解消する目的でつくられたものです。
ただ、近年の法改正、特に「制限規定」の改正に関して、最も重要なタイミングといえば、「平成30年(2018)」改正と考えます。
「それ以前の制限規定を、『柔軟性のある制限規定』に集約、整備した」
というのが一つ。もう一つの理由は、
「そのときの制限規定が、生成AIの可否に大きく影響している」
からです。というのも、
前述の第30条の2、第30条の3のように、改正されながら残っているものもあるものの、細かい制限規定が増えすぎていたんですね。これは、
日本の著作権法は、利用の目的や場面ごとに一定程度「具体的に規定」する(”個別の制限規定”)スタイル
ものだからです。それに対して、
アメリカ著作権法(107条)の「フェアユース」のような制限規定を日本も導入すべきでは?
という議論もありました。
ところでその、結構耳にする言葉「フェアユース」って何なのでしょうか。
著作物の利用について、一定の要素を総合的に考慮して、それが「公正な理由(Fair Use)」であると認められれば、その著作権者からの許諾(OK)を取らずに利用できる「一般的・包括的」な規定
のことです(アメリカでは、デジタル時代よりはるか昔の1976年の法改正で付け加えられたというからすごいのですね)。
こうした規定があるからこそ、著作権を扱う(特にインターネット関連の)新しいビジネスが、アメリカで生まれてきた、とも言われますよね。それは、「著作権法に抵触するビジネスかもしれないけど、とりあえず始めてみて、著作権侵害で訴えられたら、あとで『フェアユース』の主張が認められるかどうか裁判で決めればいい…」というスタイルが可能だからです。
そこで日本でも、「日本版フェアユース」が長年議論・検討され、それが本格的に導入されるかどうか注目されたのが、「平成30年(2018)」改正だったのですが、最終的に
日本では、「一般的・包括的」な規定の導入は見送られた
んですね。様々な意見を集約、検討した結果、「裁判で決着をつけることに慣れている・社会の仕組みもそうなっている(司法による法規範形成)アメリカ」と違い、日本では大半の企業や団体は、高い法令遵守意識がある一方で、訴訟への抵抗感もあると。
また、著作権に対する理解が十分に浸透していないことなどから、「一般的・包括的」規定を都合よく解釈しすぎて、権利侵害を助長する可能性が高まることへの恐れもある…などの理由があったようです。
そこで、日本に合っていて、それでいて従来よりも「柔軟な」権利制限として、
「権利者に及ぶ不利益に応じて、明確性と柔軟性の適切なバランスを備えた規定を整備することが適当」
という考えのもと、導入された制限規定が、
第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第47条の4(電子計算機における著作物の利用に付随する利用等)
第47条の5(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)
です。これらは、増えすぎた制限規定をある程度整理しながら、著作権を扱う新たなサービス
「AI開発」
「所在検索・情報解析サービス」
等への対応も想定しながら、規定されたものになっています。次回は、これらについて、具体的に触れていきたいと思います
(…次回は、内容的にも、間をあまり開けないようにがんばります…)。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
好評です! ONION商標の新サービス
ロゴ作成+商標登録 =「ロゴトアール®」
https://logoto-r.com/
ロゴ制作から商標登録完了まで、弁理士が一括サポート。
いいロゴに®もつけましょう!
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲