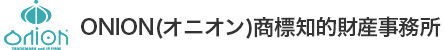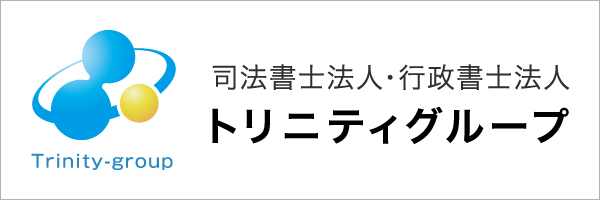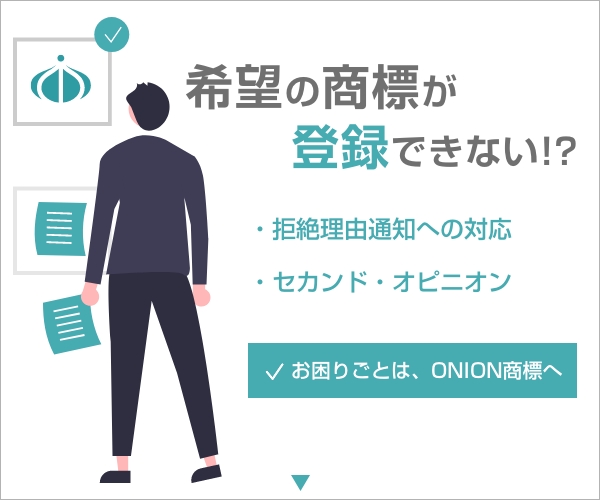ONION商標・弁理士の山中です。
技術革新等に伴い変化しつづけるエンタメ業界。そんな時代だからこそ、拠り所とすべきは「著作権法」ですが、「法」に対していきなり細かいところをつつくのではなく、「その全体や構造、考え方を『ざっくり』学んでしまうことが近道だ」という趣旨でご紹介する連載、その第14回です。
ここのところの数回、著作権の「制限規定」(※あとでおさらいしましょう)について考えていますが、今回は
【美術の著作物】
に関連する制限規定をご紹介します。
「美術」作品が、著作物であることは、論を俟ちません。著作物について規定した著作権法第2条でも、その文末に「〜、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と、”美術”という文字がありますし、
また著作物を例示した第10条1項にも、
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
とありますからね。ちなみに、これは法律の読み方になりますが、「A、B、その他のC」という表現の場合、AとBは、「Cの例示」になります。つまり、美術の著作物は「絵画、版画、彫刻」に限らない(あくまで例示)ということです。
【ざっくり著作権法】第4回「そもそも…著作物って何だ?」
http://onion-tmip.net/update/?p=878
では、他に美術の著作物としてどういうものがあるかというと、たとえば、「マンガ」もそうですし、書道家が書いた「書」なども該当し得ますよね。舞台装置とか、美術工芸品(特に一品もの)なども美術の著作物に該当し得ます。
そして、その著作者が、自分が創作した美術の著作物については、著作権(と著作者人格権)を得るわけですが、
【ざっくり著作権法】第5回「著作者が得る権利ー著作権(その1)」
https://onion-tmip.net/update/?p=922
ひとくちに「著作権」といっても、それはさまざまな「◯◯権」をまとめたような概念でしたよね。その中で、美術の著作物が関連しやすいものとしては、
たとえば、「絵画」「マンガ」のような平面のものであれば、コピー機等で簡単に「複製」できるので、「複製権」がからんできますし、もっとも、”撮影”という方法を使えば、彫刻等の立体的な著作物だって簡単に複製できます。こうして複製されたデータ等は、さらにインターネットを通じて「公衆送信」もされやすいので、「公衆送信権」などもからんできます。
中でも「美術の著作物」ならではの著作権としては、「展示権」があります。
(展示権)
第二十五条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
この条文のとおり、著作物もいろいろ種類がある中で、
展示権は「美術の著作物」と「(未発行の)写真の著作物」にしか与えられない権利
なんですね。
さて、ここまでは復習&前振り。やっと「制限規定」の話になっていきます。
原則、著作(権)者は、自身の著作物を、他の人が勝手に利用していたら、「◯◯権侵害だから、ダメ!」と止められるわけですが、
ある一定の場面では、他の人が利用していても、著作(権)者が「利用しちゃダメ!」と言えないように”制限”する規定、その名も
「(権利)制限規定」(著作権法30条〜47条の8)
がありました。
(制限規定の理由・目的などはこちら)第7回 http://onion-tmip.net/update/?p=1192
美術の著作物を、その著作(権)者以外が利用する場合、たとえば「複製」という利用を勝手にしていたら、原則は、著作(権)者が有する「複製権」侵害となるんですが、
たとえば既に説明している「私的使用目的」の複製であれば、複製権侵害にならず、だれでも使っていいよ、と第30条の制限規定で定めているわけです。
【ざっくり著作権法】第7回「他人の著作物を使っていいケースとは?ー著作権の制限規定(その1 :概要と「私的使用のための複製」)http://onion-tmip.net/update/?p=1192
そして今回は、美術の著作物についての著作権が、対象となりうる「制限規定」で、まだ説明していない重要なもの、つまり
「美術の著作物」についての「展示権」に関する制限規定
を紹介するのが一番の目的です(…あぁ、やっとここまできた)。
いくつかあるんで、順番に見ていきましょう。
<45条:美術の著作物等の原作品の所有者による展示>
第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる
美術作品(特に「絵画」などの原作品)は、売り買いされたりしますよね。しかし、そうした美術・写真の著作物の「原作品」が買った人のものになったとしても(=所有権の移転)、その著作者が持つ「著作権」は別個のものなので、一緒に移転したりしません。
ということはですよ、せっかく美術作品を買った人(買主)が、その作品を展示しようとしたら、著作者から「私の展示権侵害なんで、やめてください」と言われたら…ちょっとおかしいですよね。そのような状況を調整するために、本条(第1項)の制限規定が存在するわけです。
原作品の所有者は、原作品による展示(※コピーの展示は対象外です)は、展示権をもつ著作(権)者の許諾を取らずに、公に展示していい
わけですね。また、原作品の所有者から「同意を得た者」(例:所有者から同意を得た「美術館」等)も同様に、公に展示ができます。
しかし、この45条には第2項がありまして、
2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。
例え、美術の原作品の所有者だとしても、一般公衆に開放されている「屋外」の場所等に、「恒常的に」設置する場合は、制限規定の対象外、つまり美術の著作(権)者の展示権侵害になっちゃいますよ、ということです。
(※なお、第2項は写真の著作物の原作品は対象外なので、屋外への恒常展示もOKになります)。
なお「一般公衆に開放されている屋外の場所」は、公有地か私有地かを問わずに、ダメになります。また「一般公衆の見やすい屋外の場所」とは、建物の屋上にある広告看板などが想定されます。
<46条:公開の美術の著作物等の利用>
これは前条、つまり45条とリンクしてくる制限規定なのですが、
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
つまり、美術の著作物の原作品が、第45条2項に規定されているような
「屋外に恒常的に設置」をされている場合と、
建築の著作物(※屋外に面していて当たり前)は、原則、
他の人たちが、自由に利用ができる
(、たとえば、撮影したり、録画したり、そういうデータを公衆送信したり…がOK)というものです。
ただ、条文の最後のちょっと前に「次に掲げる場合を除き」とありますね。どういうケースが除かれるのかというと、
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
特に「美術の著作物」が対象になるのは、一、三、四ですね。一があるので、屋外に恒常的に設置された「彫刻」を、撮影したりはOKですけど、それの「レプリカ」を作ったりするのはダメよ、ということになります。
また四は注意ですね。いくら「自由に利用可」といっても、屋外に恒常的に設置された美術の著作物を、絵はがきだったり写真集だったりにして「販売目的」で、複製(撮影等を含む)するのは、NGよと。もちろんその販売もNGよ、ということです(※「無償配布」目的なら、販売目的ではないので、OKということになりますが)。
<47条:美術の著作物等の展示に伴う複製等>
「展示に伴う複製」とは、具体的には、
美術館などで展示する美術の著作物等を、紹介・説明したりする小冊子等に、一定の条件で掲載することが許される
、というものです。一応、第1項を貼りますが、長い上に….
第四十七条 美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者(以下この条において「原作品展示者」という。)は、観覧者のためにこれらの展示する著作物(以下この条及び第四十七条の六第二項第一号において「展示著作物」という。)の解説若しくは紹介をすることを目的とする小冊子に当該展示著作物を掲載し、又は次項の規定により当該展示著作物を上映し、若しくは当該展示著作物について自動公衆送信(送信可能化を含む。同項及び同号において同じ。)を行うために必要と認められる限度において、当該展示著作物を複製することができる。ただし、当該展示著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
….わかりづらいんですよね。なので、ざっくりまとめると、
①「美術・写真の著作物等の原作品」が対象。それらを、
②展示権(25条)を害することなく公に展示する者=つまり、展示権を持つ著作(権)者の許諾を得たか、前述「第45条」の制限規定によって展示できる人は、
③展示されている原作品の「観覧者」のために、
④「解説・紹介を目的とする『小冊子』」に、その展示している著作物を掲載してもいい。
→カタログ、目録、図録などは「小冊子」扱いですが、「豪華本」はアウト
→観覧者のために(無償配布でなく)「販売」してもいい。
⑤ただし、その予定人数を大幅に上回る部数を刷って、観覧者以外にも販売するのは、アウト
ということになります。展示会の適切な解説・紹介が「小冊子」でなされれば、鑑賞者の助けになりますから、このような制限規定があるのですが、逆に観賞用の画集のような豪華本レベルになったり、小冊子でも一般販売までされてしまったら、著作(権)者の複製権等がおびやかされてしまいますから、細かく条件が定められているわけです。
なお、平成30年(2018年)の著作権法改正(31年1月1日施行)により、本条は第2項・3項が追加されました。これは、これまでの小冊子での解説・紹介に加え、タブレット端末等の電子機器へ作品画像(著作物)を掲載できること等を規定したほか、展示作品に関する情報を広く一般公衆に提供することを目的として、作品画像のサムネイル画像(作品の小さな画像)をインターネットで公開できること等が規定されました。ただ、これらの場合でも、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」という条件は、第1項と同じです。
<47条の2:美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等>
こちらは平成21年(2009年)の法改正で追加された制限規定です。
美術品等も、2000年代に入ってインターネットオークション等の「非対面での商品取引」が急速に普及しました(※絵画等を売り出すのが「譲渡等の申出」というわけです)。
こうした取引の際には、美術品や写真の商品紹介用の画像を載せることは、商品の内容を正しく把握し、安心して取引するためには、とても重要ですよね。しかし、それまでの著作権法に照らし合わせると、こうした掲載も、複製権や公衆送信権の侵害を構成してしまうという問題がありました。そこで、
譲渡権等を侵害しないで美術品や写真の譲渡等を行うことができる場合には、その申出のための複製または自動公衆送信が、著作(権)者の許諾なしに行えるようにした
制限規定です。この条文もかっこ書などが多くてわかりづらいのですが、一応貼ります。
第四十七条の二 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。
条文からポイントを抽出すると、
①原作品の所有者だけでなく「複製物」の所有者 も対象で、
②譲渡権(二十六条の二第一項)・貸与権(第二十六条の三)の侵害とならずに、譲渡・貸与しようとする場合は、
③権原を有する者又はその委託を受けた者(※画廊・オークション会社等)は、
④「その申出の用に供するため」
→ネットオークション等(※ただ、条文上、非対面の販売に限定されているわけではありません)
⑤複製又は公衆送信(※著作物の写真等の「アップロード」を含みます)をしていい。
⑥但し!著作(権)者の利益を不当に害しないための措置として政令で定めるものを講じる場合に限定
→具体的には「コピープロテクションをかける」「画像のサイズ・精度(解像度)を落とす」という措置を講じなければいけない
という感じです。
******
今回はとても長くなってしまいましたが、美術関連の制限規定については、展示権の話から始めて、ひとまとめの記事にしたかったため、ご容赦ください。
ということで、次回はそろそろ「制限規定」も大詰め、しかも近年ホットな「生成AI」と関連する規定に入っていきたいと思っています。
→次回第15回はこちら http://onion-tmip.net/update/?p=3318
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
好評です! ONION商標の新サービス
ロゴ作成+商標登録 =「ロゴトアール®」
https://logoto-r.com/
ロゴ制作から商標登録完了まで、弁理士が一括サポート。
いいロゴに®もつけましょう!
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲