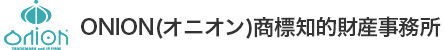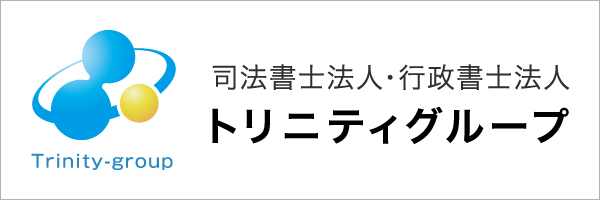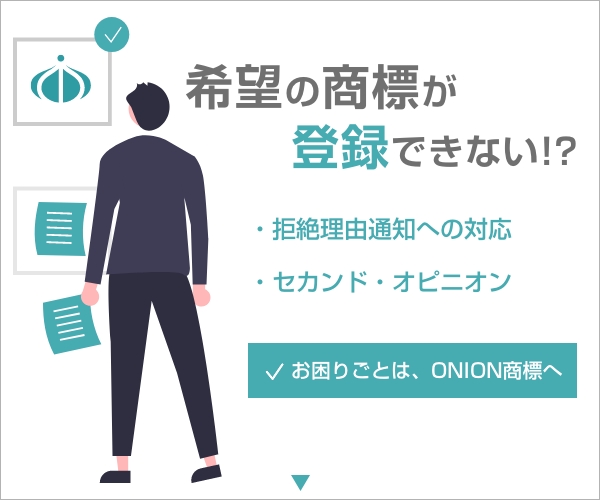ONION商標・弁理士の山中です。
今回の投稿記事は、当職が開設しているもう一つの事務所「ENTiP(行政書士、音楽コンサルティング業務も行っています)」のウェブサイトに投稿した、こちらの記事
「IP時代・グローバル時代のアーティスト/バンドのネーミングで気を付けるべきこと(前編)」
https://entip.jp/topics/300/
に続く、後編となります。
本来、一度つけたらそう簡単には変えたくない、アーティストのネーミング(芸名や、バンド名・グループ名等)ですが、それを「変えなければならない」事態として、前編の序章に挙げられていた以下の2つ
◎そのネーミングだと、他者のIPを侵害してしまう。
◎ネーミングを変えずに、他者のIPの侵害を回避しようとすると、本来払わなくてもいいはずの費用を払わなければいけなくなる。
これらは、具体的にいえば、
「そのネーミングでは、商標権が取れない(=商標登録ができない)から」
というケースです。
前編第2章⑵で、現在のアーティスト活動(の重要な側面として)、
「マーチャンダイジングの時代」
だという話をしています。そして特に、こうしたマーチャンダイジングの範囲は、
「非音楽業界」のブランドによる、商標登録とバッティングしがち
です。アーティストの人気が徐々に上がってきて、「そろそろ商標登録するか!」と思って調査をしたら、同じや類似の名称のファッションブランドが存在し、「被服」(ティーシャツなど)などの範囲で先に商標登録されてしまっていた…などというケースが、よくあるのです。
商標権はとても強い権利ですから、先に商標登録している権利者から、「権利行使」といって、
「その商標、うちのだから(or うちのと似てるから)使わないで」
と言われたら、原則、従わなければなりません。もし、使うことを「許諾」してもらえるとしても、ライセンス料を払う必要も出てくるでしょう(そんなのもったいなくないですか?)。
ライヴ活動でも、マーチャンダイジングにも使えない…となったら、やはりそのアーティスト名を名乗り続けることは困難です。
だからこそ!今回お伝えするポイントは、ぜひ「結成直後」、つまり
「まだアーティスト名を決めてない」
「今なら変えても大丈夫」
という段階からご検討いただきたい内容です。「まだ契約無いから」とか、「配信もしたことないし」とか、気にしなくて大丈夫。むしろ、そういう早い段階から意識しておくほど、効果的な内容です。
以下、備考ですが、
*基本的には、アーティストの皆さんを対象にして書きますが、そうしたアーティストと接するマネージメントやレーベルの方々にも参考になれば幸いです。
*当職の経歴から、音楽アーティストを対象とした書きぶりになりますが、「ライヴ」も「マーチャンダイジング(物販、アーティストグッズ)」も実施するタレント/各種アーティストの方々にも、当てはまる内容です(※特に弁理士目線の部分は)。
第4章 商標登録できないかもしれない?危険度大なネーミング
(1)「既存のワンワード」はつけたくなるところだけど…
「既存のワンワード」って、アーティスト名にしたくなるんですよね。これは第2章(1)でも述べたとおり、①耳馴染みがよく、②簡単に読めて…というブランド認知のプラスになる要素を満たしているわけですから。
「THE ◯◯」みたいにワンワードに冠詞がついただけのネーミング
も同様です。
ただ、こうしたネーミングは、第2章(1)でのもう一つの要件「③ありきたりでない」を満たしません。そうなると、先に誰かに商標登録出願/商標登録をされてしまっている文字と、かぶる可能性が高くなる、すなわち商標登録がしづらくなるわけですから、あまりおすすめできないのです。
「よくある名前(と読み方は同じ)なんだけど、その『綴り』を通常とは変えた」?
という場合はどうでしょう?商標登録の観点からいえば、あまり解決策としては機能しません(ちなみに、綴り違いですらそうなんですから、アルファベットの「大文字・小文字」の差異だけでは、商標的には「同一」だと考えてください)。
まず第一の理由として、商標の類否(類似か否か)は、
・外観(文字の綴り)だけでなく、
・称呼(読み)
・観念(意味)のどれかが同一であれば、「商標類似」と判断され得る
からです。中でも、特に重視されるのは「称呼」です。多少綴りが違っても、既存のワンワードと同じ読み方であれば、「類似の商標」と判断される可能性が極めて高く、それが先に出願→登録されていたら、重複する範囲では商標登録できません。
そしてもう一つの理由として、
・商標の「読み方」は、出願人は指定できない
からです。
【本当はコワイ商標の話】商標の称呼(読み)って、自分で決められるの? ー 商標権の価値を貶める間違った方策とは? https://onion-tmip.net/update/?p=1307
確かに、変わった綴りにすれば、「(同じように読ませたい)既存のワンワード」が仮に商標登録されていても、称呼(読み)が異なると特許庁審査官に判断されて、商標非類似と判断される可能性もあります。
しかし、一方で、「自分が意図する読みが生じない」と判断される可能性があるということは、仮に「(同じように読ませたい)既存のワンワード」が、あとから他人に出願されたとき、自分が先に商標登録していたとしても、「商標非類似」と判断されてしまい、その出願を排除できないことになり得るということです。
(2)「慣用語句・熟語になっている2ワード、3ワード」も危ない
理論的には「2ワード」「3ワード」など、ネーミングを構成する要素が増えれば、誰かのネーミングとバッティングする可能性は下がるはずですが、それが「慣用句」や「熟語」として意味が通るものであれば、それだけ「他の人も思いつく/使いたくなる」可能性はあがりますから、やはりバッティングしてしまうリスクは高いと思います。
ちなみに、「長いアーティスト名」が流行した時代というのがあって、
※フランク・シナトラが音楽界から映画界に進出することを伝える新聞記事の見出しから派生した「都へ出てきて堕落する」というニュアンスの慣用句的隠語に由来するんだそうです。
これは「アーティスト名は短いのが普通」だった時代へのアンチテーゼだったと思うんですが、商標登録のためだけに長いアーティスト名を選択するのは、ちょっと本末転倒ですよね。純粋に「そのネーミングがいい」と思えば、長いほうが他者とバッティングする可能性は減るでしょう。
なお、あまり長いと「キャッチフレーズ」や「スローガン」と受け止められる可能性があります。ただこの点も、かつてはそのような商標は登録されづらかったのですが、現在はあまり気にしなくていいかなと思います。
【本当はコワイ商標の話】「キャッチフレーズ」って、結局、商標登録できるの?できないの?(何のためにするの?)
https://onion-tmip.net/update/?p=1181
(3)なぜ「アルファベットの組み合わせ」は危険なのか
それはやはり「パターン」が少ないので、他の人とアイデアがかぶりやすい→先に商標登録されてしまっている可能性が高くなる、ということです。
そもそも、アルファベットは26文字しかないわけですから、
3文字なら、26 x 26 x 26 = 17,576 「しか」パターンがないわけです。
もちろん、同じ「3文字」だとしても、その商標を使用しようとする商品・サービスの範囲が重複しなければ、併存して商標登録は認められますが、
「音楽の演奏」といったサービス(役務)が分類されている区分「第41類」は、他にも「教育系」の役務も分類されていますので、たとえ「(その3文字と)同じアーティスト名、聞いたことないから大丈夫だろ」と思っても、実は「非音楽系」「非アーティスト系」の事業者が、同じ3文字を、重複する範囲で既に商標登録してしまっている可能性は十分にある、ということです。
4文字なら、17,576 x 26 = 456,976
とパターンは格段に増えますので、重複する可能性は低くなりますが、組み合わせによっては重複可能性が高まります。
たとえば最初の文字が「J」は、”JAPAN”の頭文字で多く使われますし、「I」なんかも”INTERNATIONAL”の頭文字でよく使われます。そうなると、実質的に残る3文字での勝負、になってくるので、やはりアイデアがかぶってしまう可能性は、それなりにあるということです。
また、4文字だと「読み(称呼)」が、アルファベットを一つずつ読む以外にも生じてきますよね。たとえば、当職のニックネーム「ICHI」であれば、称呼は「アイシイエイチアイ」だけでなく「イチ」も生じるでしょう。そうすると、称呼が増える分、称呼が同一という理由で「商標類似」と判断され得る先願商標が、増えていってしまう、ということです。
ちなみに「2文字」だったら?
2文字からなるアーティスト名も存在することは存じ上げてますが、商標弁理士の立場からは「なるべくやめてほしいな…」というアイデアです。これは、他者とかぶりやすいという以前に、
「原則、アルファベット2文字以下は、商標登録が認められない」
のです。登録が認められない「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」(商標法3条1項5号)に該当するためで、これは商品等の”目印”になる力(識別力)がないため、そして特定の誰かに独占させるべきではない、という理由からなんですね。
ちなみに、アルファベットに「数字」を加えて3文字になったとしても、同様の理由でアウトです。
【本当はコワイ商標の話】商標の「簡易検索」の落とし穴!早いもの勝ちと言われる商標登録の「誤解」とは?
https://onion-tmip.net/update/?p=1334
※こちらで「同じ3文字でも、併存登録されるケース」や、なぜ2文字ではだめなのか(記述的商標、という拒絶理由)について説明しています。
どうしてもアルファベット2文字(以下)のアーティスト名がいいということなら、その2文字に図形要素を加えた「ロゴマーク」であれば、図形部分に識別力が認められて、登録になり得ますけどね。そうでなければ、よっぽどアーティストとして著名になれば、逆に識別力が認められることもあるでしょうが、そこまでは商標権での保護が難しくなってしまいます。
そういや、昔、アルファベット1文字のアーティストがいたな…と思ったけど、”+(プラス)”もついてました。
第5章 商標登録の費用をどう捻出するか?(他の人に出してもらうときの注意点)
(1)商標登録にはお金がかかる
前章まで、商標登録は原則「早い者勝ち」というルールの中で、「こういうネーミングは、他の人のアイデアとバッティングしがちだから危ない!」という観点で述べてきました。
しかし、そういう「かぶりがち」なネーミングであっても、プロによる商標調査をして、セーフ(同一又は類似のネーミング等が、商標登録したい範囲で、まだ他の誰にも先に商標登録出願されてない)ことが分かった場合、すぐに出願できるなら、いいんですよ。まさに「早い者勝ち」な中で、一番早く、勝てそう、ということですから。
ただ、商標登録には費用がかかります。それを「結成したてのバンド」「活動したてのアーティスト」が、他にお金もかかる時期+音楽活動から収益が発生しない時期に、自分たちで負担するというのは、なかなか難しいものがあります。
【ONION商標】商標登録にかかる費用
https://onion-tmip.net/timeline.php#price
(※もちろん、配信等により直接世の中に音楽を発信している方で、思わぬ収入が上がったら、すぐ商標登録は検討して欲しいところですが、そういう方は次章に飛んでください)
(2)マネージメントに費用を出してもらう場合の注意点
そこで、まずはアーティストとして王道に頑張っていただくとして、その結果
「一緒にやりませんか?」
と、マネージメント(事務所、プロダクション)から声がかかり、所属(専属契約等の契約)を結ぶケースを想定しましょう。すると、
アーティストにかわって、マネージメントが商標登録費用を出してくれることが多いです。
その場合、ただ、お金を出す分「商標登録によって発生する商標権は、マネージメントに帰属する」でいいですか?と言われるでしょう。出願人がマネージメントの場合、商標権者もマネージメントになります。
※審査時に、そのアーティストが全国的に知られている存在=著名になっていると、本人以外は登録が認められない(商標法4条1項8号の拒絶理由)ので、マネージメントが商標登録を受けることについての「承諾書」をアーティストは出す必要があります。
商標登録の費用を出してもらってるんだから、ある程度は仕方ないですよね。ただ、その後の取り扱いについて、契約書等で気をつけてほしい点がいくつかあります。
*商標権をもとにマネージメントが行うビジネスに、(その登録商標を付した)マーチャンダイジングがあります(グッズとか、物販ともいいますね)。このマーチャンダイジングの売り上げは当然マネージメントに最初入りますが、ここからどれだけの割合(%)がアーティスト側の取り分となるか、これは納得のいく数字でサインしてください。
*商標権がマネージメントに帰属するのは「アーティストが、マネージメントと(専属等)契約している期間のみ」とすべきです。つまり、アーティストが何らかの理由でそのマネージメントと契約終了する場合は、「アーティスト・サイドに、一定の条件で、譲渡する」という契約内容になっていることを確認してください。
「これからお世話になるマネージメントに、『契約終了する場合』の話をするなんて!」と思われるかも知れませんが、契約(書)というのは、まさかの時に向けて、ある程度の対応指針を定めておくものです(うまくいかなくても、うまくいき過ぎても、そうした「指針」がないと、もめてしまったりするのです)。
*上記「契約終了時に、アーティストに商標権の譲渡」する場合の、「一定の条件」が、無理筋でないことも確認しておきましょう。「商標登録時の費用(※商標権の残存期間に応じて、一部控除)」で譲渡してくれる、というのが真っ当な条件だと思います。
(3)「マネージメントが名付け親」の場合の商標権について
最近は少なくなってきたようにも思いますが、デビュー前からマネージメントに発掘・育成されてきたアーティストなどで、「アーティストのネーミングをマネージメントがする」つまり名付け親である、というケースがあります。このような場合は、アーティスト本人も気づかないうちに、マネージメントが商標登録していることがあります(※これ自体は、アーティスト名に積み重なり得るブランド力を保護するものですから、正しい行動ではあります)。
そして、見事のそのアーティストが成功し、著名となった場合でも、やはり何らかの理由で、アーティストがそのマネージメントを離れたい(独立、移籍)という決断をすることは、起こり得る話です。もちろん、しかるべきタイミング(※契約更新時、など)でですよ。
その際、かつては、「マネージメントを離れるなら、その名前は使わせない。」とアーティスト/タレントに通告するようなケースも、あったと言われています。もし使用したら、「その名前の商標権は、こちら(※マネージメント)が持っているから、商標権を行使して、使用差し止めをする」というロジックです。極端なケースになると、その名前が「本名」であるにもかかわらず、商標権を盾にとって、使用をさせないということもあったようです。
しかし、そこまで移籍を拒む場合は、そのアーティスト等が、かなり成功している、つまりその名称=商標が、著名になっていることが想定されます。となれば、その商標は、そのアーティスト等「本人」と紐づけられて著名性を獲得しているわけで、マネージメントサイドが商標権者だとしても、その使用を「本人」たるアーティスト等が使用できない、というのはあってはならないことだと考えます。また、
極端な「移籍を拒む」対応は、商標法とは別に、独占禁止法に抵触する、
という考え方が一般的になってきました。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20241226-OYT1T50004/
こうした趨勢を把握しているマネージメントであれば、アーティスト(名)の商標権の取り扱いについて、真っ当な条件で譲渡をする契約内容にしていることが妥当ですから、その点も契約時には確認するようにしてください。
(※但し、マネージメントがそのグループのコンセプトを決定し、オーディション等を経てメンバーを決定・結成したグループで、メンバーが変更になりながらも、そのマネージメント所属のグループとして続いていく…というようなケースであれば、そのマネージメントが「グループ名」の商標権を保持し続ける、脱退したメンバーにはグループ名の使用権原がない…という契約だったとしても、妥当かなと思います)。
第6章 その他の商標登録にまつわる注意事項(身バレ、仲間割れ…等)
(1)自分で商標登録する場合の注意点<開示される情報>
前章では、アーティストが「所属するマネージメントに、商標登録をしてもらう」前提で説明しましたが、
アーティスト自身で商標登録をするケース
を考えてみたいと思います。
作品を直接配信するなどして、マネージメントに頼らず成功するアーティストも増えてきている昨今、「商標登録費用を自分で捻出できる」ケースも増えているでしょう。
自分で考えたアーティスト名/グループ名。それを商標登録=商標権を自分で取得するのは、本来は正しい流れですし、商標登録出願は、「法人」だけでなく、「自然人」すなわち人間個人名義でも出願できるのです。
ただ、その場合の注意点として「身バレ」があります。どういうことかというと、
*個人(自然人)で出願する場合、出願人の名義は「戸籍名」でしか出願できません(芸名やビジネスネームは不可)
*また、出願時には「居所」も記載する必要があります。こちらは「自宅」とか「本籍地」である必要はなく、「書類が郵送されたときに受け取れる」住所である必要があります。つまり、契約しているオフィスの住所などで可。
というのが商標登録出願の前提なのですが、
出願すると、戸籍名や居所が「公開」されてしまいます。
具体的には、商標公報や、「J-PlatPat」などのデータベースで開示されます。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
つまり、VTuberや、匿名で活動しているアーティストが、そのアーティスト名を商標登録しようとしたとき、自身個人で出願すると、その本名(戸籍名)や、オフィス等の住所が、紐づけて公開されてしまうということです。
そういう方は、(既存の事務所に所属しないのであれば)自身で「会社組織(法人)」を立ち上げたタイミングで、法人名義で出願するのが、身バレしない方法になるかと思います。
(2)グループで使用する商標の注意点
グループ、バンドといった形態のアーティスト。つまり、複数のメンバーで構成されるアーティストの場合、そのアーティスト名は、そのメンバーみんなで使用する「商標」、ということになります。そんな場合は、どのように商標(権)を保護できるのでしょうか。
かつては、グループの解散時などに、一部のメンバーが勝手にそのグループ名を商標登録しようとしたり、あるいは独立を望むメンバーがそのグループ名を使用するのを止めるために、残りのメンバーが商標登録しようとしたり…という泥沼な状況になることもあったと聞きます。
商標登録出願をするときに、複数人が「共同」名義で出願することが可能です。そうすると、商標登録によって発生する商標権も、その複数人で「共有」することができます。一見、フェアな気がしますが、この方法には落とし穴があるのです。
*共有する商標権は、他のすべての商標権者の承諾がないと、第三者へのライセンスや譲渡ができません(商標法35条で準用する特許法73条1項)
これはまだいいとして、もう一つのルールが、
*共有する商標権は、その個々の商標権者が、誰もが自由に、その商標を使用することができます(商標法35条で準用する特許法73条2項)
つまり、みんなで合意の上で解散したのに、そのメンバーの一人が勝手に、そのグループ名(登録商標)を、合法的に使用できてしまう、ということになります。
こうしたケースを防ぐためには、
商標権の共有に加えて「その使い方について、メンバー間で取り決めを決めておく」
必要があります。例えば、「全員がそろった時しか、その登録商標(グループ名)は使用できない」など、メンバーが納得のいくルールを、仲の良いうちに決めておくことをお勧めします。
あとがき:ONION商標は、アーティストの商標登録の力になります
弊所ONION商標では、
音楽アーティスト向け 商標登録パッケージ
「STAART」https://onion-tmip.net/staart.php
というプランを設定しております。こちらを安価と思っていただけるかどうかはわかりませんが、商標制度を熟知し、そして音楽を中心としたアーティストへのリスペクトに溢れる弁理士が、アーティスト、そしてアーティストを信じサポートされる皆様(マネージメント、レーベル等)の御力になれるよう、議論を尽くして設計した内容です(、そしてさらに、個別の事案に応じて、柔軟に内容を変更し、御見積りからご相談いただけます)。
是非今回の記事を御読みいただき、アーティスト名の商標登録に興味を持っていただけましたら、お気軽にご相談ください。