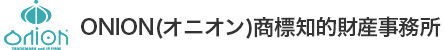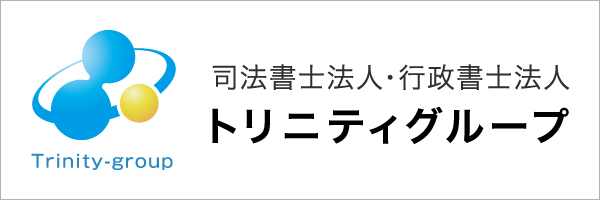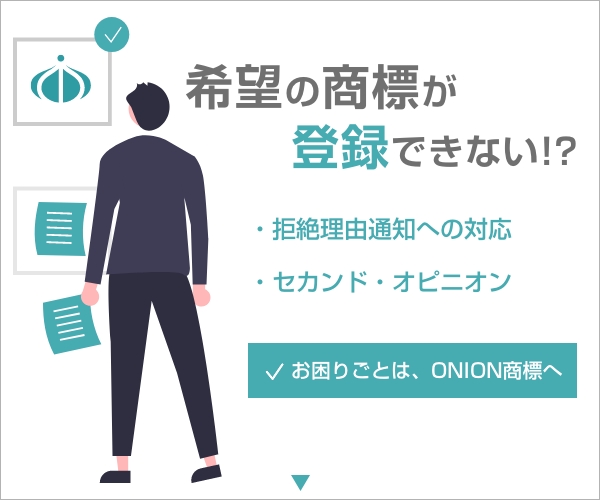今回ご紹介するのは、「肖像権」と「パブリシティ権」のおはなしです(本来、もっと早く取り上げるべきだった、重要なトピックです!)。
どちらも聞いたことはある、という方は多いと思うんですが、違い?と言われると、理解している方は少ないかもしれません。
そこで、今日はその違いの要点だけでも、掴んでいただけるように、お話をしたいと思います(ま、正確には、違いだけじゃなくて、共通する部分もあるんですけど、そこも含めてね)。
1.肖像権(ロックファンのA君の悲劇)
まず、こんなケースをイメージしてください。
A君は、大都会東京で、普通に暮らす小市民でした。そんな彼の唯一の楽しみは、大好きなヘヴィ・メタルのライヴで暴れること(ま、パンクでもなんでもいいんですよ、ここは)。
しかし、それを他の人には隠していました。なぜならA君の彼女はロックが大嫌いで、「ロックなんかダサイの聴いてる男とは、絶対つきあわないわ」と公言しており、知られたら確実にフラレてしまうな、と思ったからです。
いつものようにライヴで盛り上がった数日後、写真週刊誌を見てびっくりしました。行ったライヴを取り上げた記事で、自分がモッシュしているのがしっかり写った写真が掲載されていたのです。
「どうしてくれんだよ!これがバレたら彼女にふられて、自分の生活は台無しになってしまうじゃないか!!」
….という文句を、A君が週刊誌にいうときの根拠に出来るのが『肖像権』です。
肖像権は、特に◯◯法で規定されているものではなくて、判例や学説が積み重なって認められるようになった権利です(ちなみに、日本の旧著作権法、つまり明治時代のそれには、そのような規定があったそうですが、現行の著作権法にはないんです)。
ですから、何の法文集をみても、しっかり定義は書いてありません。ただし、一般的には、
*自己の肖像をみだりに作成されない権利、あるいは
*作成された肖像を無断で利用されない権利
と理解されています。具体的には、
① 撮影されることを拒絶する権利としての、肖像権
② 作成され(てしまっ)た肖像の利用を拒絶する権利としての、肖像権
です(もうひとつ③がありますが、それは後述)。
上述のA君の場合は、ちょっとやわらかい事例にしましたけど、日本では昭和30〜40年代に、政治的なデモ行進に参加した人が、撮影され(、メディアで公開され)てしまい、それが原因で所属している会社や団体から不利益を被ることがあったんですね。そうした事件に関する裁判がきっかけで、判例が積み重なっていった(つまり、肖像権が確立していった)わけです。
では、そうした判断の根拠、って話なんですけども、保護対象が“人の肖像”ということで、肖像権は伝統的に“人格権”として認識されてきました。
私法上の権利って、大きく“人格権”か“財産権”に分類できるんですよね。で、人格権っていうのは、名誉・氏名・肖像・プライバシーなど、人の精神的、人格的利益を保護する権利の総称です。ですから、大元の根拠ということでいうと、憲法13条=個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉、ってことになるんですね。
もちろん、『肖像権』を盾に訴えたからといって、裁判で勝てるかどうかはケース・バイ・ケースですが、上述のA君のケースの場合、この自身の写真掲載によって、彼女にふられ、精神的苦痛を被った…というところまでは、「肖像権侵害!」として主張として筋が通ってますよね?
2. パブリシティ権(著名ロック評論家となったA君の主張)
こんどはこんなケースを考えてください。さっきのA君の続きです。
その後、彼女にふられた痛手を振り切り、逆にヘヴィ・メタル評論家として、自身のブログでの評論や投稿を積み重ね、ついには雑誌やテレビ・ラジオからも出演依頼があるほどの知名度を獲得しました。
もう、ここまで来ると、ライヴにも招待されちゃうんですね。
ライヴ会場に、ヘッドフォンをしながら入ったA君。いつの間にか誰かに写真を撮られたようですが、もう人気者だし、今一番話題のバンドのライヴに、A君がいるのは公然の事実。あまり気に留めていませんでした。
一ヶ月後、ある電気店のポスターを見てびっくりしました。自分が使っているB社のヘッドフォンのポスターに、自分の写真と、「メタル評論家・Aも使ってる、このヘッドフォン!」というキャッチコピーが掲載されていたのです。電気店に聞いたところ、このポスターが掲載されて以降、このヘッドフォンの売上げは激増しているんだとか。
「ナンだよ、明らかにオレ様の知名度がこのヘッドフォンの売上げに寄与してるんじゃないか。オレをこういう風に使うときは、ギャラは◯◯万円て決めてるんだよ。実際、B社じゃなくて他の会社からも、ヘッドフォンのキャラクターで、オファー来てたんだぜ」
…こういう文句を、B社に言うときの根拠に出来るのが、『パブリシティ権』です。
A君は既に有名人なので、B社のポスターに載る前からみんなに知られてるわけですから、B社のポスターに載ったことのせいでプライバシー等が害されて「幸福が害された」とはいいようがありません。つまり、無名の一般人のように『肖像権』では訴えることは難しいでしょう。
しかし、無名の一般人にはない、有名人だからこその社会的評価や名声等があり、その氏名や肖像等には、商品等の宣伝、販促に効果があります。つまり、人を惹き付ける
「顧客吸引力」
ですね。この効果によって、A君は稼いだりすることもできるわけで、これは財産的価値があることになります。つまり、こうした…
顧客吸引力のもつ経済的な利益ないし価値を、有名人本人(A君)だけが有する”財産権”として認めたものが、パブリシティ権
です。
以上、「パブリシティ権と肖像権の違い」を簡単に述べましたけど、全く関係ないわけではないんですね。さきほど、肖像権のところで、「3つめの肖像権があって、後述する」って言ったのを覚えてらっしゃいます?
その「3つめ」が、“肖像本人の有する財産的利益、財産権としての肖像権(肖像を営利目的で利用することを禁止する権利)”、すなわち、今でいうところの「パブリシティ権」なんですよ。
つまり、肖像権の概念の一部だったものを、今は性質上分けて、「パブリシティ権」と呼んでいるかたちなんですね。同じ人に根付く権利でも、パブリシティ権は、“財産権”グループに属します。なので、“人格権”として認められていった、現在の定義の肖像権とは区別されるわけです。
ちなみに、まだ世間には知られていないA君の「アシスタント」は、同じようにポスターに写っていたとしても、彼のパブリシティ権は認められないでしょう。誰も知らない、認めてないんだから、顧客吸引力がアシスタント君にはないからです。
つまり、有名人ほど、氏名・肖像の持つ経済的価値が強くなる。すなわち、顧客吸引力が大きくなる。よってパブリシティ権は強くなるということです。
(逆に有名人ほど、肖像権は制限されるということも言えます。)
3.パブリシティ権の重要な判例「ピンク・レディー事件」
ここまでを理解して、ずいぶんニュースでも取り上げられた、パブリシティ権に関する最高裁判例「ピンク・レディー事件」にふれておきましょう。
ピンク・レディーといえば、1976年デビュー〜81年の(一旦の)解散まで、日本中を席巻した女性デュオですが、この事件は比較的最近、2012年2月2日のものです。
どんな事案だったかというと、
ある週刊誌が、ピンク・レディーの代表曲5曲における振り付けを利用したダイエットに関する「ピンク・レディーdeダイエット」と題する記事(全3頁)を、作りました。
これら写真自体は、週刊誌の発行元が持っていた写真なんですけど、このピンク・レディーの両名が写っている写真(14枚)を、ピンク・レディーの承諾は得ずに、掲載したところ、
ピンク・レディーの両名が、同誌の出版社を訴えた、
という事件です。
提訴したピンク・レディー側にしてみると、「実質的なグラビア記事で、ピンク・レディーに夢中になった世代を引きつけて利益を得ようとした」
と、主張したわけですね。彼女たちの「顧客吸引力」を利用して、利益を得ようとしてるじゃないの、って主張ですね。
この事件で、最高裁は、判決理由の中で、「パブリシティ権」を、
「(著名人などの)商業的価値に基づく人格権のひとつで、顧客吸引力を排他的に利用する権利」
と初めて定義しました(上の「おはなし」の中で触れた定義とほぼ同じですね)。
最高裁が定義したわけですから、既判力も強いですから、より「パブリシティ権」というものが認められたといえるんじゃないでしょうか。
それで、パブリシティ権侵害になる具体的ケースとして、
(1)肖像それ自体を鑑賞対象とする商品に使う
(2)商品の差別化に使う
(3)商品の広告として使う
…など「専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合」と説明。ですから、グラビアやキャラクター商品などは侵害に当たるとの判断を示したものです。
そして、この裁判の結論、つまり判決はだったかというと、
ピンク・レディーが敗訴しました。
その判断はどうだったかというと、
*著名人は社会の耳目を集めやすく、報道や創作物など正当な表現行為で氏名や肖像を使われるのは一定程度、受忍すべき。
*今回の記事は、ピンク・レディーそのものを紹介する内容ではなく、ダイエット法などを紹介する程度にとどまっている。
→よって「顧客吸引力の利用が目的ではない」
と、結論づけたわけです。
ただ、ここで間違えてほしくないのは、今回のピンク・レディーが敗訴したのは、「パブリシティ権というものが認められなかった」のではないし、
彼女達が著名であることには疑いないですから「彼女たちの写真にパブリシティ権がない」と言われたわけでもないんです。
あくまで、前述の定義に照らして判断した結果、ピンク・レディーが有するパブリシティ権が、今回の事案においては侵害されたとは言えない、と判断された、ということです。
—————————————————-
以上、簡単ではありますが、パブリシティ権と肖像権について説明してきましたが、いかがだったでしょうか。今後は、これらの権利についてあまり説明なく記されている「はしょった」記事を見ても、一体これはどちらについて争われてるんだろう?ということはわかるかと思います。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
好評です! ONION商標の新サービス
ロゴ作成+商標登録 =「ロゴトアール®」
https://logoto-r.com/
ロゴ制作から商標登録完了まで、弁理士が一括サポート。
いいロゴに®もつけましょう!
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲