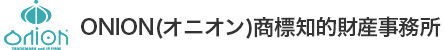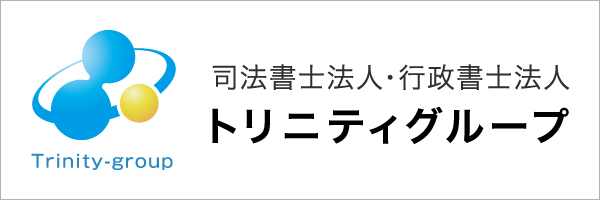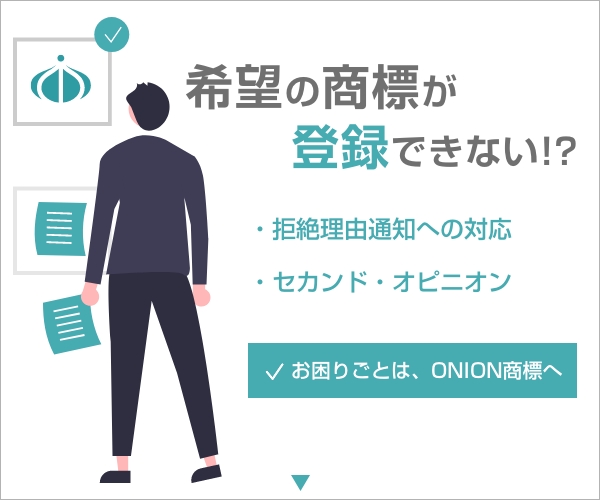先日、弁理士の中でも時折使う言葉が、ニュースから流れてきたので、びっくりしました。
退職代行「モームリ」を警視庁が捜索、報酬目的で顧客を弁護士に紹介した非弁行為容疑(読売新聞オンライン)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20251022-OYT1T50037/
「非弁行為」
という言葉です。
一般的には聞き馴染みのない言葉だと思いますが、今回の事件についてさまざまなニュースがわかりやすく解説してくれています。
退職代行「モームリ」の複数関係先を強制捜査 「社員全員の前で…」元従業員が証言 専門家が指摘する“退職代行の落とし穴”とは|TBS NEWS DIG
https://youtu.be/mw159NJCpkY?si=nCFP1xsc_dCKIorb
弁護士法72条は、以下のように規定されています:
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
ざっくりいうと、
弁護士資格を持たない者が報酬目的で法律業務を行うことや、あっせんすること
を、「非弁行為」として禁じているわけです。
それに対して、今回当事者となっている退職代行業者は、依頼者の退職に伴い「交渉」(※法律業務ですね)が必要となった場合に、同社が有償(報酬目的)で弁護士にあっせんしていた疑いで、警視庁が捜査したわけですね。
また、今回のケースでは、あっせんを受けた弁護士事務所も、弁護士法違反容疑で捜索されたと報道されていますが、
弁護士が、弁護士資格を持たない者からあっせんを「受ける」ことも非弁行為
なんですね。
(非弁護士との提携の禁止)
第二十七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
ところで、われわれ弁理士にも、”弁”の文字がついてますよね。そして、弁理士制度についてさだめる「弁理士法」というものが存在します。そちらの「第75条」を見てください。こちらが、
弁理士法における「非弁行為」
を禁止した条文なんです。
(弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限)
第七十五条 弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。
赤字は筆者が入れたものですが、この部分をのぞくと、弁護士法72条と似ています。逆にいうと、弁護士法72条より、下線部(対象となる業務)の内容が、こちらのほうが細かいですよね。これこそ、
弁理士の「専権業務」
を示す部分です。かつて、こちらの記事で触れたのですが、
【弁理士のつぶやき(ときに長め)】 「あらためて『弁理士』という仕事を説明してみる〜ドラマ『それってパクリじゃないですか?』によせて」
http://onion-tmip.net/update/?p=1202
弁護士は原則、すべての法律事務について弁護士が業務権限を有していますが、
日本では、弁護士業務の範囲内で一定の法律分野に限定された業務権限を有する職種(隣接法律専門職)が設置されており、
上記の下線部の業務については、弁護士を除けば
「弁理士しか行うことができない」
わけです。つまり、これらの業務を、弁理士(又は弁護士)以外が行えば、それが
「弁理士法における、非弁行為」
ということになります。故に、私たち弁理士も、弁理士資格をもたない方が、報酬目的で弁理士業務を行うことや、そうした方から業務のあっせんを受けることは、慎まなければいけませんし、見逃すことはできません。
非弁行為の防止に向けた措置について(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/ryui/hiben_boushi.html
また、「隣接法律専門職」の国家資格をもつ我々も、それぞれの資格の「業際」については日々気を付けています。
たとえば、我々弁理士が、弁護士や、司法書士等それぞれの専権業務について、報酬を得る目的で業務を承ってしまえば、これは非弁行為になってしまうのです。これは絶対に避けなければいけません。
もっとも、この士業同士の「業際」は、一般の方には難しいですし、一部の士業に独占されているのではなく、「他の士業の人も扱っていいよ」という業務もあるので、余計わかりづらいんですね。
弁理士=知的財産のエキスパート、という認識はお持ちいただければ嬉しいですが、日々の事業のご相談ごとについて、どんな士業に相談すればいいかわからない場合、まずはお気軽に、弊所弁理士までお問い合わせください。もし、それが弁理士の資格では対応できない場合は、提携する他の士業を速やかにご紹介させていただきますので!
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
好評です! ONION商標の新サービス
ロゴ作成+商標登録 =「ロゴトアール®」
https://logoto-r.com/
ロゴ制作から商標登録完了まで、弁理士が一括サポート。
いいロゴに®もつけましょう!
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲