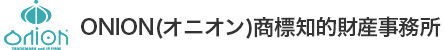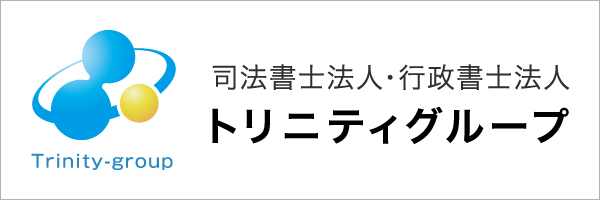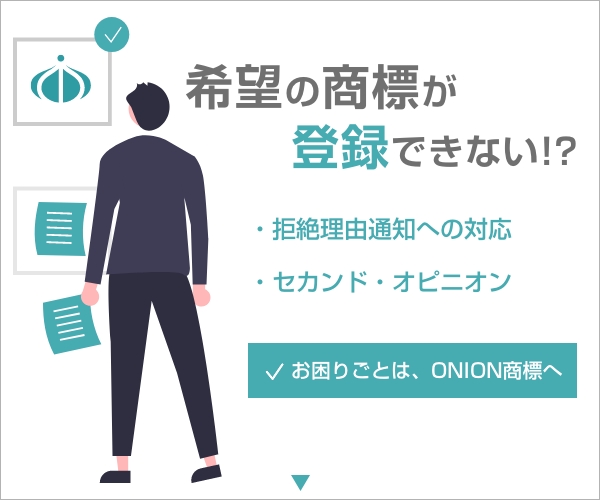ONION商標・弁理士の山中です。
技術革新等に伴い変化しつづけるエンタメ業界。そんな時代だからこそ、拠り所とすべきは「著作権法」ですが、「法」に対していきなり細かいところをつつくのではなく、「その全体や構造、考え方を『ざっくり』学んでしまうことが近道だ」という趣旨でご紹介する連載、その第16回です。
数回にわたって、著作権の「制限規定」についてご紹介してきましたが、
第7回「他人の著作物を使っていいケースとは?ー著作権の制限規定(その1 :概要と「私的使用のための複製」)
https://onion-tmip.net/update/?p=1192
前回に続いて、
【デジタル時代の?制限規定】
についてご紹介していきます。まずは、内容的に非常につながりが大事な前回の内容を少しおさらいします。
第15回(※前回)「他人の著作物を使っていいケース?- 著作権の制限規定(その9:「デジタル時代の?制限規定①〜フェアユースって日本にあるの?ないの?そもそも何?」」)
http://onion-tmip.net/update/?p=3318
デジタル化・ネットワーク化の進展等に伴う著作物の利用環境の変化を受けて、著作物の利用の円滑化を図る観点から、平成末期から法改正(制度改正)が順次行われてきました。具体的には、「著作権者の権利を制限して」著作物の利用をしやすくする「制限規定」が追加されてきたのですが、
個別具体的な制限規定が、細かく増えすぎていたんですね。にもかかわらず、それでも新しい著作権を利用したビジネスへの対応を考えると、不十分であった、と。
一方、アメリカの著作権法にある「フェアユース」のような、「一般的・包括的」な規定も検討されましたが、さまざまな理由から日本には馴染まない、と。
そこで、日本に合っていて、それでいて従来よりも「柔軟な」権利制限として、
「権利者に及ぶ不利益に応じて、明確性と柔軟性の適切なバランスを備えた規定を整備することが適当」
という考えのもと、平成24年(2016)に改正・導入された制限規定が3つあります…というのが、前回の終わりでした。では今回は、それらを1つずつ見ていきたいと思います。
(※著作権法における「電子計算機」は、ざっくり「パソコン」と思って読んでいってください。)
実は、この条文(制限規定)は、それまでに増えていた制限規定を、整理しながら、新しい要素も加えたものになっています。
では、どのように整理したのかというと、まず、制限規定を、以下の3つの「層」に分類したんです:
[第1層] 権利者の利益を通常害さないと評価できる行為類型
[第2層] 権利者に及び得る不利益が軽微な行為類型
[第3層] 著作物の市場と衝突する場合があるが、公益的政策実現等のために著作物の利用の促進が期待される行為類型
このうち、第3層は、「ざっくり著作権法」でもかつて見てきた、「引用」(第32条)「教育関係」(第33条等)…など、従来からあるものが多く該当するのですが…
第8回「他人の著作物を使っていいケースとは?ー著作権の制限規定(その2:引用)
https://onion-tmip.net/update/?p=1321
第10回「他人の著作物を使っていいケースとは?ー著作権の制限規定(その4:教育関連)
https://onion-tmip.net/update/?p=2075
…近年増えてきた制限規定の中には、[第1層]、[第2層]に該当するものも多かったのです。
ではまず[第2層]から行きますか。たとえば、
第47条の5 電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等
こちらですが(※条文省略します)、かつて旧47条の6「インターネット情報検索のための複製等」という制限規定がありました。情報検索サービス事業者が、そのサービスの提供過程で行われる著作物の利用を、セーフにしたものでしたが、これらの対象を、
「書籍検索」なども含む、ビッグデータを活用して新たな知見・情報を創出する「所在検索サービス」、
論文剽窃検証や口コミ分析など「情報解析サービス」も対象にし、
これらに付随して著作物を利用することを「セーフ」にできるよう、柔軟な規定にしたもの
です。ただ、柔軟とはいえ、細かく要件はあるのですが、その要件には
「必要な限度内の利用であること」
「利用する著作物が著作権侵害により公衆に提供・提示されたものであることを知りながら利用せず、また、著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害さないこと」
等が含まれるのは、当然かと思います。そうしないと、権利者に及ぶ不利益が「軽微ではなくなってしまう」おそれがありますものね。
次は上述の[第1層]です。これに該当する制限規定としては、もともと、パソコンやサーバーにおける「キャッシュ」のための複製(旧47条の5・47条の8・47条の9)とか、複製危機の修理・保守・交換や、サーバーの滅失等に供えた「バックアップ」のための複製(旧47条の4・47条の5)などがありました。
これらをまとめながら、より柔軟性の高い内容にしたのが、
第47条の4 電子計算機における著作物の利用に付随する利用等
です。複雑な条文なので貼りません(※条文省略します)が、ざっくりまとめると、
第1項が「キャッシュ等」関係
→情報処理を円滑又は効率的に行うためのキャッシュ等に係る著作物の利用は、(要件あるものの原則)セーフ。
第2項が「バックアップ等」関係
→著作物のコンピュータ等における利用ができる状態を維持・回復するためのバックアップ等の利用は、(要件あるものの原則)セーフ。
というように定められています。それぞれ要件は細かいのですが、第1項・2項に共通するものとしては、
・必要な限度内の利用であること
・その著作物の種類や用途などから判断して、著作権者の利益を不当に害さないこと
の2つがあります。対象となる行為は「権利者の利益を通常害さないと評価できる行為」ではあるものの、念の為、といったところでしょうか。
さて、この[第1層]の行為類型をまとめた制限規定は、もう1つあります。
第30条の4*(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
*平成24年改正で導入された条文が、平成30年さらに改正されています(以下「新30条の4」という場合があります)。
ちょっと条文のタイトルが長いんですが、これ「著作物の定義」を思い出すとわかりやすくなります。
(第2条1項1号)
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
そもそも、「思想又は感情を創作的に表現したもの」というのは、著作物の本質なんですね。つまりこの制限規定は、
「著作物の本質」の享受を目的としない利用
と読み替えられそうです。結構、「包括的」なイメージがある表現ですね。では、実際の条文も見てみましょう。
(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
こちらには、平成24年に導入された制限規定:「著作物の利用に係る技術開発・実用化の試験のための利用」(旧30条の4)を、「電子計算機による情報解析のための複製等」(旧47条の7)などをまとめ、対象を柔軟にしつつ、新たにこれから想定される
「サイバーセキュリティ確保等のためのソフトウェアの調査解析(リバース・エンジニアリング)」なども対象にできる内容
になっています。もっといえば、
これから新しく創出されるサービスが、著作権を「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」に該当し得るものであれば、とりあえずローンチすることも可能
となるわけですね。
しかし、この「新30条の4」については、もう少し語りたいことがあります。それは、上述の(旧47条の7)「電子計算機による情報解析のための複製等」を取り込んで、対象を柔軟にした「ことによる」ターゲットの具体的な説明です。
旧47条の7では、対象となる情報解析の方法が「統計的」な解析に限定されていました。それが今回の条文では、「情報解析の用に供する場合」とだけ書いてあります。これは、
「AI開発のためのディープラーニング」が対象にできるような文言
にしたものなのです。
次回は、この新30条の4と、昨今の生成AIの関係について、掘り下げてみたいと思います。
次回第17回はこちら→ http://onion-tmip.net/update/?p=3740
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
好評です! ONION商標の新サービス
ロゴ作成+商標登録 =「ロゴトアール®」
https://logoto-r.com/
ロゴ制作から商標登録完了まで、弁理士が一括サポート。
いいロゴに®もつけましょう!
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲