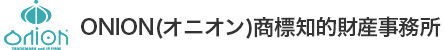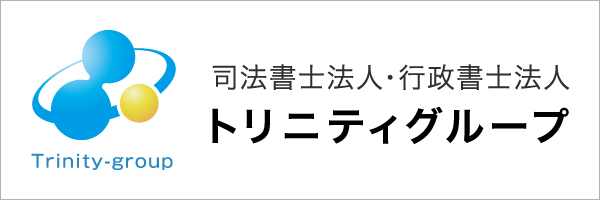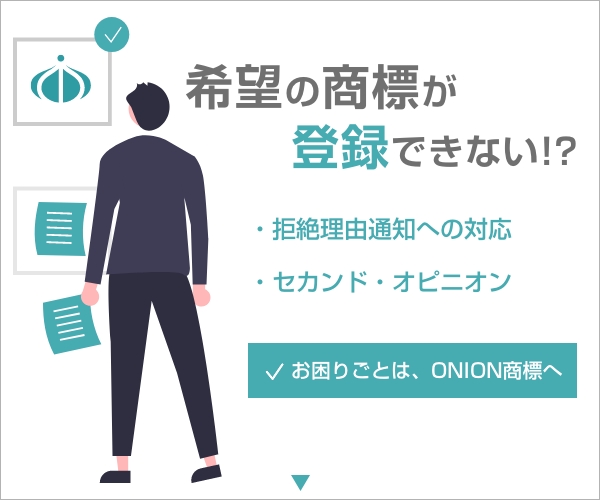少し前のニュースになってしまいますが、エンタメを愛するONION商標の弁理士としては、どうしても触れておきたかった話題があります。
AI音声「アニメ・映画の吹き替えに使わないで」 音声業界が会見(朝日新聞)
https://www.asahi.com/articles/ASSCF3GBMSCFUCVL03HM.html
敢えて断言しようかと思いますが、日本人で、声優さんとその「声」に対して、リスペクトを持っていない人は、極めて少ないのではないでしょうか。
最近のアニメが好きな若い世代はもちろんのこと、アダルト層だって子供の頃からアニメに接して育ってきているわけですし、シニア層であれば、洋画や海外ドラマの「吹き替え」で、お馴染みな「声」が存在していたはずです。もちろん、声優さんは一人で様々な声を使い分ける方も少なくないですが、そのバリエーション含め、声優さんの技術であり、個性であり、アイデンティティなのかなと感じますよね。
しかし、そんな「声」が、「生成AI」が一般的となっていく時代において、危機にさらされています。
進化し続ける生成AIの技術をもってすれば、声優さんらの声を学習させ、いとも簡単に「ほぼ同じ」ような(音)声を作成できてしまうわけです。
当然、なんらかの権利や制度で「声」を保護すべきと感じる人が多いと思いますが、ここで問題になるのは、
そのものズバリで「声」を守る権利がないのです。
たとえば、こうした声が認知されるきっかけになっているのは、アニメやドラマといった「著作物」を通じてですから、
声は「著作権」や「著作隣接権」で守られないのかな?
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、声優さんが歌う曲(音楽の著作物)や、セリフ(言語の著作物)等は著作物だとしても、「声」自体を、著作権法で定める著作物の定義に当てはめることは、無理があります。そうなると、著作物の創作者=著作者が得る「著作権」も、声優さんは得られないということになります。
【ざっくり著作権法】第4回「そもそも…著作物って何だ?」
https://onion-tmip.net/update/?p=878
また、著作隣接権は、著作物の創作者ではないものの、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家等に与えられる権利です。声優さん等は「実演家」に該当することは間違いないのですが、
実演を生成AIに入力するといっても、その実演自体を使うのではなく、その特徴を解析して、同じ音声波形を生成する方式の場合は、「合成された音声は元の音と物理的に同一ではない」ため、著作隣接権の侵害にはならないという説が有力なのです。
しかし、なぜこのような音声を作り出そうとする人がいるかといえば、声優さんによるその「声」が世間に広く認知・認識され、人気を獲得しているからですよね。当然、商業的価値も伴うものです。やはり、
何らかの方法で「声」を保護すべき
であることは、国(経済産業省)も認識しているんですよね。
声優のAI音声、無断利用に警鐘 経産省、違反の恐れを例示(47NEWS / 共同通信)
https://www.47news.jp/12559948.html
まず、こちらで示されているのが、「権利」違反ではないけれど、「制度」違反。具体的には、
「不正競争防止法」違反の可能性
です。通称「不競法」と呼ばれていますが、ざっくりいえば、経済が発展していくのに必要な「競争」において、「不正」な競争行為を禁じるなどして、経済の健全な発展に寄与することを目的とするものです。
【知財キホンのキ】商標と関連アリ・商標以外もカバーする?「不正競争防止法」って何だ(1)
https://onion-tmip.net/update/?p=518
上記引用コラムにもありますが、不競法の第2条第1項第1号〜22号に、具体的な「不正競争行為」の類型が定められています。
さて、「声」に関して、今回の経済産業省の見解で挙げられた具体的な事例を1つ紹介しますと、
<事例③>ある人物と同一の声を出力することができる生成AIを用いて、当該生成AIに当該人物の持ち歌ではない曲を歌わせ、それを動画投稿プラットフォームに投稿した場合
こういう場合は、当該人物の声が「周知」であれば、同法第2条第1項第1号、すなわち
「周知表示に対する混同惹起行為」
に該当するとして、対処しうるとされています。
他人の商品やサービスを示す表示(商品等表示)として、需要者の間に広く認識されているものと同一または類似の表示を使用し、その結果、消費者が商品やサービスの出所を誤認・混同してしまうような行為を指すものですが、周知な声は「商品等表示」に該当するということですね。
また、もし、打ち消し表示(例:「AI○○に歌わせてみた」)が付されている場合には、同1号では対処が難しいものの、理論上は「著名性」が認められれば、同項第2号、すなわち
「著名表示冒用行為」
にて対処可能、とされています。こちらは、全国的に著名な「声」であれば、誤認・混同が生じなくても、該当し得るということになります。
もうひとつ、「声」を守れる可能性がある権利としては、
「パブリシティ権」
があります。「著名人の氏名・肖像」には、人を惹きつける力=顧客吸引力が認められますが、これは財産的価値を生みます。たとえば、著名人の肖像の「トレーディングカード」などは買いたいという人が多いでしょうし、著名人の名前や肖像に対し「お金を払うので、弊社の広告に使わせてください!」というオファーもあり得るでしょう。
このように、顧客吸引力のもつ経済的な利益ないし価値を、著名人本人だけが有する”財産権”として認めたものが、パブリシティ権です。我が国には、パブリシティ権を明文化した法令は存在しませんが、学説や判例の積み重ねによって認められるようになった権利です。
【知財キホンのキ】今からでも間に合う!「肖像権」と「パブリシティ権」の違い【エンタメ従事者必須】
https://onion-tmip.net/update/?p=3096
では、「氏名」や「肖像」と同様に、声優さんの「著名な声」に、パブリシティ権は認められるのでしょうか?
パブリシティ権の有名な判決に、平成24年の最高裁判例「ピンク・レディー事件」があり、今回の経済産業省の見解でも紹介されています。
判決では、パブリシティ権の客体である「肖像等」については、(中略)「声」は「肖像」そのものではないとしても、
「肖像等」には「声」が含まれる
と明示されたんですね。そして、パブリシティ権が及ぶ場合として例示に、「声」を当てはめて、
①声自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合
②商品等の差別化のために声を商品等に付している場合
③声を商品等の広告として使用している場合
「声」についてパブリシティ権に基づく保護が可能と考えられると、述べられています。
こちらをふまえ、著名人の「声」データの取扱いについて、生成AIを利用した場合について検討すると、
*生成AIに声のデータを入力するだけでは、上記の場合に該当しない
*生成AIを利用して、著名人の「声」とほぼ同一のような「声」のデータを生成したとしても、生成しただけでは、上記の場合に該当しない
ので、パブリシティ権侵害には該当しない可能性が高いですが、
*生成AIを利用して、著名人の「声」とほぼ同一のような「声」のデータを生成し、それを「販売等商用利用」、つまり上記の①~③に該当するような使用をすれば、これは「パブリシティ権侵害」に該当する可能性が、極めて高い
といえるでしょう。
****
生成AIを上手に活用することは、これからの時代は不可避だと思いますが、あくまで知財・クリエイティヴィティ・個性・技術などがしっかり保護されるのが大前提ですよね。私達の生活を豊かにしてくれる声優さんたちの「声」が、しっかりと保護されることを弊所弁理士も強く望むところです。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
好評です! ONION商標の新サービス
ロゴ作成+商標登録 =「ロゴトアール®」
https://logoto-r.com/
ロゴ制作から商標登録完了まで、弁理士が一括サポート。
いいロゴに®もつけましょう!
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲