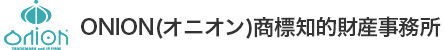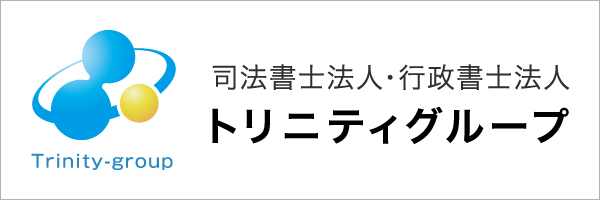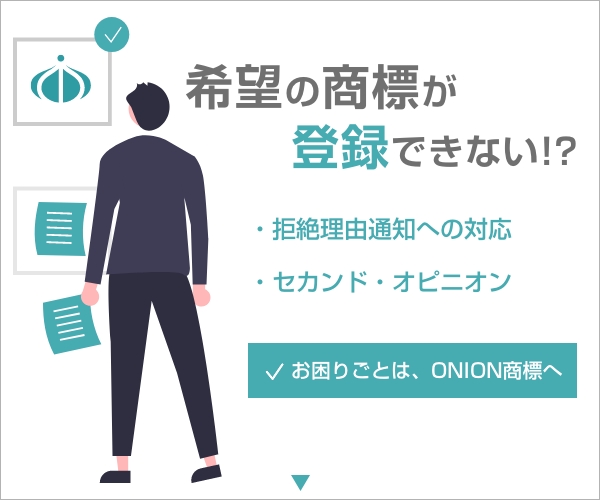ONION商標で、商標権・商標登録制度について説明する記事の中で、「商標の識別力」については、過去何度か触れてきました。
商標は、商品やサービス(役務)の”目印”として使っていくものなので、他者の商品や役務と区別する力、いわゆる「識別力」がないと、商標登録が認められません。
そしてこの「識別力」の有無は、商標と、使用する商品・役務との関係によって変わってきますし、またタイミングによっても変わってきます。
【本当はコワイ商標の話】商標出願を急がなきゃいけないのは「早い者勝ち」だけが理由ではないです〜登録できたかも!?ができなくなるケースとは?
https://onion-tmip.net/update/?p=2316
商品名やサービス名などのネーミング、すなわち「文字の商標」を決めるとき、「商標登録の可能性が高いものを選択する」という観点から言えば、
明らかな造語
を選択すればいいわけです。
(※もちろん、その他の登録要件、例えば「重複する商品等の範囲に、同一又は類似する先願商標がないかどうか」も必要ですが、造語であれば、他の人のネーミングとかぶる可能性も、一般的には低くなります。もちろん調査はすべきですが)。
しかしながら、
『記述的商標』だとして拒絶されるかもしれないけれど、それでも出願→登録を目指す「意義」があるケース
も存在すると、弊所では考えます。
そもそも、「記述的商標かも?」というような文字商標は、「その商品やサービスの内容(品質、質)を、顧客にイメージさせやすい」という強みがあるのです。
もちろん、完全に「その品質、質を示すにすぎない」とまで説明的になってしまえば、記述的商標として拒絶査定(登録できない)わけですが、審査段階で「いや、まだ識別力がある」と認められれば、登録査定(登録可能)となります。
こうした文字商標は、上述の「強み」がありますから、もし登録できたらメリットは大きいです。その後に「この商標は、弊社の登録商標です」というように商標の普通名称化を防止しながら、ブランドとして育てていくことも可能です(※ただし、そこには待ち構える苦難もあります…そこは後述します)。
では、この”チャレンジ”をする意義があるのは、具体的にどのようなケースでしょうか?
【ケース1】自分で思いついた文字商標だけど、やや説明的かな?と不安
まず「やや説明的だな(たとえば、「よくある文字2語」とか、商標の中に形容詞が入っているとか)」と一般の方が思ったとしても、商標専門の弁理士が見ると「あ、これはちゃんと『造語』になってます。識別力が認められる可能性が高いです」というケースもある(逆に、一見して「NGです」というケースもある)ので、まずご相談いただければと思いますが、
逆に、弁理士がその商品・サービスのジャンルに疎いと、あまり聞きなれない文字(の商標)なので識別力が認められるかな…と思っても、実はその商品等の業界では一般的に使用されている(商品等の)名称であって、もう識別力が認められなさそう、というケースもあります。
したがって、専門家(商標弁理士)だとしても、調査検討は重要になってきます。商標法、商標審査基準等に照らし合わせながら進めていくわけですが、特にポイントとなるのは、
①既に、同一の文字商標(あるいはほぼ同義語の文字商標)が他人により出願され、(記述的商標として)拒絶となっていないか
②商標登録したいと思っている文字を使用している同業他者が、インターネット上でいるかどうか(いるとしたら、どれくらいいるか)
③相談者の、その(文字)商標の使用実績
といった観点です。①で拒絶事例がなく、②で国内使用事例がなければ、登録のチャンスは見えてきますし、それが③で補強されていきます。
もちろん「記述的商標に該当しないかもしれない」→「登録できる可能性がある」ということは、「他人が既に登録している可能性もある」ことになりますから、「早い者勝ち」の観点からの調査へと続くことになります。
【ケース2】自分がその商標のパイオニアだと思っているが、他者の使用例が出てきた
これは特にコンサルティング系のサービス提供者に多いんですが、そのコンサルティングの内容をイメージさせるような、肩書きというか、役職名のような商標です。
「その名称でサービス提供を始めたのは自分が最初(パイオニア)!」というのは、その業界で活動を続けてこられた方なら、わかっているでしょうし、そこは信用に足ります。ぜひこの方にこそ、商標登録をしていただきたいところです。
しかし、「他者の使用例が出てきた」ということは、つまり上記【ケース1】で挙げた、検討の観点
②商標登録したいと思っている文字を使用している同業他者が、インターネット上でいるかどうか
において、これが存在し、そして目立つようになってきている、ということです。これはかなり「記述的商標」へと近づいてしまっている段階といえます。
いち早く出願をすべきですが、【ケース1】で挙げた観点
③相談者の、その(文字)商標の使用実績
は、パイオニアである以上、一番積み重なっているはずですし、また他者使用例が、このパイオニアと何らかの関係があること(※たとえば、コンサルティングの指導を受けた受講者)が証明できれば、
「他の人の商標としては識別力は認められないけれども、このパイオニアが使う限り、識別力が認められる」
という余地はあるものと考えます。
【ケース3】登録できないかもしれないけど、「他人も登録できない」ことをはっきりさせたい
上記【ケース1】の検討の観点で挙げた、
①既に、同一/類似の文字商標が他人により出願され、(記述的商標として)拒絶となっていないか
で、拒絶例が見つかった場合、中でも「拒絶査定→拒絶査定不服審判の請求」を経て、それでも「記述的商標」であるとして登録が認められなかった事例が見つかった場合は、
その文字は、(よほど誰かが使用し続けて識別力を獲得しない限り)誰にも登録は認められない文字列ですので、商品などには自由に使用できることとなります。
【本当はコワイ商標の話】商標登録は早い者勝ち…のはずが、時間が経った方が登録可能性が上がる商標がある!?
https://onion-tmip.net/update/?p=2983
しかし、そのような拒絶事例が存在しなければ、「本当に誰も登録できない商標なのか!?」ははっきりしないこととなります。そこで、
「登録が認められる可能性は、厳しいかな…でも、ワンチャン狙いたい」
その上で
「登録できなくても、せめて『他の誰も登録できない』ことをはっきりさせたい」
というマインドでトライできるのであれば、いち早く出願すべきということになります。
しかし、(上でも少し触れているのですが)「誰も登録できない」と言い切るには、ただ出願→拒絶査定では不十分であり、一般的には「拒絶査定不服審判」まで経る必要があると言われています。そこまで費用と時間がかかることは覚悟の上でチャレンジしなければなりません。
【本当はコワイ商標の話】 拒絶された商標登録が、後から他人に登録されてしまうことがある?
https://onion-tmip.net/update/?p=292
商標登録が認められた!しかし待ち構える「茨の道」とは!?
上記のケース1〜3のいずれにしても、チャレンジした結果、商標登録が認められたとしたら、本当によかったです。ただ、ここで安心はできません。
商標登録に対しては、「商標登録されるべきじゃなかった!」として、他者が取消や無効を申し立てることのできる制度があります:
①「商標登録異議申立」
商標掲載公報(※登録された商標が広く公開される公報)の発行日の翌日から起算して、2ヶ月以内、「誰でも」申立て可能。
②「商標登録無効審判」
登録から5年間(※「記述的商標」すなわち商標法3条1項各号該当の場合)は、利害関係者は請求可能
特に「記述的商標かどうか、際どかった商標」の登録については、同じ文字を使用したい同業他者が、「特定の一社(者)に登録されたら、困る!登録されるべきではない!」として、これらの制度を利用してくる可能性は、通常よりも高いといえます。
つまり、せっかく登録が認められても、その商標権が「強い商標権」として安定するまでは、かなり長い間「不安定」な状況が続く、といえます。
またもちろんその間も、「普通名称化」を防ぐ取り組みも必要です。
【本当はコワイ商標の話】 「普通名称化」~せっかくの登録商標が効力のないものに?
https://onion-tmip.net/update/?p=419
特許庁の判断とは別に…世間一般からの「炎上」リスクはないか?
仮に、特許庁(の審査官)が、登録可能性を認めた(文字)商標だとしても、その文字が実際は一定のジャンルで、かなり多くの人に愛されていた文字・名称である場合、それを「独り占め」することにもなる商標登録に対して、SNS上等での「炎上」が起こる場合もあります。
【ONION商標・弁理士の眼】「ゆっくり茶番劇」続報〜放棄された登録商標に対する「無効審判」の意義とは?
https://onion-tmip.net/update/?p=1362
あくまで商標は、ビジネス(商品の販売や、サービスの提供)のために登録するものですから、炎上してまで商標登録を狙う、というのは趣旨と反するでしょう。
一定のジャンルにおいて、複数の人たちが既に公共的に使用している文字を、独占しようとしたら、どのような状況になるか、そのジャンルに精通された事業者の方が一番よくおわかりだと思いますので、そのような場合の「トライ」は控えることを強く推奨します。
「記述的商標」の拒絶理由を、事前回避する策とは?
その文字に(指定する商品等との関係において)識別力がなさそう、それを理由に拒絶されそう、ということであれば、
「図形要素と組み合わせた商標(ロゴマーク)として、出願する」
という拒絶(理由通知)の事前回避策があります。これは、少なくとも「図形」部分には識別力が認められるため、記述的商標とは判断されないということですね。
ただ、この方策には、デメリットもあります。それは、
文字の部分の識別力の有無が曖昧になる
という点です。例えば、指定商品等の「普通名称」とか、わかりやすく識別力がない文字なら別ですが、本稿で検討してきたような「文字商標として、登録されるかどうか」微妙なケースで、この方策をとった場合は、文字自体には識別力が認められるのかが、曖昧なままになります。
そうなってくると、含まれる文字自体については、必ずしも使用を独占できないこととなります(※同じ文字を含む後願商標を拒絶する効力や、一定の牽制効果はあるにしても)。
また、登録商標は「そのまま使用する」ことが大前提ですので、ロゴマークとしてではなく、文字のみを使用していた場合など、正しく登録商標を使用していなかったとして、「不使用取消審判」を請求されるリスクにもさらされます。
この方策は、あくまで図形商標(ロゴマーク全体)としてブランド力を築く覚悟が求められます。
本当に「際どい文字」にチャレンジする意義はあるか!?
いくつかのケースと共に、「記述的商標」かどうか、際どい商標の登録に関して、検討してきました。
「無理かも!」と思い込んでしまうのは勿体無いので、ぜひ商標専門の弁理士にご相談いただきたいですし、自分がパイオニアであるという場合は、チャレンジする意義は十分あると思います。
しかし、登録までの様々なハードルや、(登録してからも)内包するリスクがあることもお伝えしてきました。これらを考慮の上、
「それでも商標登録にトライしますか?」
「『他のネーミングを考える』という方策を取ることは考えられませんか?」
と、冷静に自問自答も、していただければと思います。
もちろん、「商標専門」弁理士事務所・ONION商標は、冷静な判断に向けたコンサルティングをさせていただくことが可能です。お気軽にご相談ください。
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
好評です! ONION商標の新サービス
ロゴ作成+商標登録 =「ロゴトアール®」
https://logoto-r.com/
ロゴ制作から商標登録完了まで、弁理士が一括サポート。
いいロゴに®もつけましょう!
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲